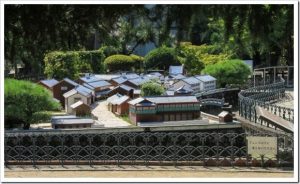八月十八日の政変で政治の中心である京都から追放されてしまった長州藩。
しかし、彼らは長州で大人しくしてはいませんでした。

長州・土佐の尊皇攘夷派たちは公武合体派が主流となっている京に潜伏し、次なる一手を画策します。
池田屋事件
元治元年6月5日(1864年7月8日)、京都三条木屋町にある旅籠・池田屋に新選組が襲来しました。
池田屋には、御所焼き討ちなどの計画を企てていた長州藩・土佐藩の尊攘過激派の志士が潜伏していました。
新選組が池田屋襲撃に至るまでの経緯を考えてみましょう。
池田屋事件経緯
八月十八日の政変で長州藩は京を追われることになりました。
朝廷の中でも過激な思想を持っていた尊攘派は追放され、公武合体派が主流となっていました。
失脚した尊攘派たちは、京に潜伏し勢力挽回の機会を目論んでいました。
京都守護職を担っている会津藩は、新選組(壬生浪士組)を京都市内の巡回、警備に当たらせ京の治安維持に励んでいました。
元治元年5月下旬頃、新選組諸士調役兼監察であった山崎烝・島田魁らが不審な動きをする人物の存在を突き止めました。
古高俊太郎
文政12年(1829年)4月6日に、大津代官所の手代・古高周蔵の子として俊太郎は生まれました。
母は公家・広橋家の家来の娘です。
古高家は長州藩毛利家の遠縁に当たると言われています。
16歳の頃、父が山科の毘沙門堂門跡に仕えることになり、京都へ移住した俊太郎は、尊皇攘夷を唱える梅田雲浜に弟子入りしました。
文久元年(1861年)、筑前福岡藩黒田家御用達の枡屋の養子となった古高俊太郎は枡屋喜右衛門と改名しました。
枡屋喜右衛門は、古道具・馬具など古器骨董商として商いをしつつ、尊皇攘夷派の宮部鼎蔵や有栖川宮と交流し、長州藩の間者として活動していました。
諸大名や公家の屋敷に出入りし諜報活動を行い、武器・弾薬などの調達を担っていました。
諸藩の御用達でもあったので、武士が店に出入りしても不自然ではなく、要人を匿ったり久坂玄瑞や桂小五郎らを有栖川宮と繋ぐなど、尊攘攘夷派に貢献していました。
元治元年6月5日(1864年7月8日)、枡屋に新選組が踏み込み俊太郎は捕縛されました。
店にあった武器弾薬は押収され、諸藩浪士との書簡や血判状も発見されました。
俊太郎は壬生屯所の前川邸の蔵に捉えられ、新撰組局長・近藤勇や副長・土方歳三らから苛烈な取り調べを受けました。
2階から逆さ吊りにされ、足の甲に五寸釘を打たれ、釘が貫通した足の裏に百目蝋燭を立てられ火をつけるなどの酷い拷問を受けたとされています。
- 長州藩による御所の焼き討ち
- 佐幕派公卿の中川宮幽閉
- 京都守護職松平容保ら佐幕派大名の殺害
- 孝明天皇を長州へ連れ去る計画
等を自白したという説と、自白には応じていないという説があります。
いずれにせよ、長州藩や尊攘派との関わりが判明、潜伏していた志士たちの集会があると分かり、池田屋事件へと発展していきます。
俊太郎はその後、六角獄舎に収容されました。
禁門の変で発生した火災(どんどん焼け)が獄舎付近まで広がったため、火災に乗じて逃亡させることを恐れた役人により、未判決のまま他の囚人とともに斬首されました。
享年36歳でした。
池田屋襲撃
尊攘派志士の会合が行われるとの情報を得た新選組は、直ちに京都守護職・松平容保に報告しました。
会津藩と桑名藩も加わり、大捕物となるはずでしたが、会津藩と桑名藩は準備に手間取り、迅速に行動できたのは新撰組だけでした。
新選組34名は、会合が行われているとされる旅籠を探すために、隊を3つに分けて探索を開始しました。
一方は新人隊士を多く含む土方隊12名、近藤隊は試衛館からの手練、沖田総司・永倉新八・藤堂平助ら10名、そして井上源三郎隊12名でした。
これには諸説有り、池田屋と四国屋の2つに絞り、近藤隊10名、土方隊24名で二手に分かれて探索したとも、会津藩のリストをもとに3つの隊に分かれて探索したとも言われています。
22時すぎ、京都三条木屋町にある池田屋にて会合中の志士を発見した近藤隊は、表口に3人、裏口に3人を配し、近藤・沖田・永倉・藤堂の4人で内部に踏み込みました。
池田屋の主人・惣兵衛が2階の志士らに新選組の襲撃を知らせると、その後を近藤が追い、抜刀した志士らと激しい斬り合いが始まりました。
新選組の襲撃を受けて、浪士たちは1階に逃れようとします。
近藤は2階を沖田1人に任せ、1階で逃げようとする志士らを追い詰めます。
しかし、戦闘の最中に、労咳を患っていた沖田が倒れ戦線から離脱。
1階中庭付近を担っていた藤堂も鉢金を取ったところで額を切られ戦線離脱。
新選組は劣勢を強いられました。
裏口を守っていたのは奥沢栄助・安藤早太郎・新田革左衛門。
近藤らの強襲を受けて十数人の浪士が2階から飛び降り、脱出を図りました。
土佐脱藩浪士の望月亀弥太らは裏口から300m程北へ向かえば長州藩邸があるため、裏口を守っていた3人に襲い掛かります。
奥沢が死亡し、安藤・新田も深手を負い、この1か月後に死亡しました。
望月もこの戦闘で負傷し、長州藩邸付近まで逃げ延びたものの追手に追い詰められ自刃しました。
部屋に居た志士は20名以上、数に劣る上に、沖田・藤堂が戦線離脱。
新選組は劣勢に陥りますが、後に土方隊や井上隊が応援に駆けつけると形勢は逆転しました。
尊攘派9名(宮部鼎蔵・北添佶摩ら)を打ち取り、4名を捕縛。
逃げた志士たちも、市中掃討に駆けつけた会津藩と桑名藩らにより、20名あまりが捕縛されました。
この市中掃討戦でも激戦が繰り広げられ、会津藩は5名、桑名藩は2名、彦根藩は4名の即死者を出しました。
長州藩の桂小五郎は、会合へ参加予定でしたが、早く着きすぎたため対馬藩邸の大島友之充と談話していたため、難を逃れたといいます。
池田屋事件の影響
京都の危機を未然に防いだとして新撰組の名は天下に轟きました。
しかし、尊攘派は吉田稔麿・北添佶摩・宮部鼎蔵・大高又次郎・石川潤次郎・杉山松助・松田重助などの死亡により大打撃を受けました。
この事件で多くの藩士を失った長州藩は、激昂しました。
八月十八日の政変での屈辱、そして池田屋事件と続き、長州藩の怒りは爆発し、とうとう京都に向けて挙兵を開始したのでした。
禁門の変の経緯
八月十八日の政変以降、長州藩内では武力でもって長州の無実を訴えようとする真木和泉・来島又兵衛らの進発論派とそれを抑える桂小五郎・高杉晋作・久坂玄瑞らの慎重派とに分かれていました。
池田屋事件で多くの藩兵を殺されたとの報を受けた長州藩は、慎重論から一気に進発論へと傾きました。
長州藩の三家老(福原元僴・益田親施・国司親相)らは藩主の冤罪を天皇に訴えるとして挙兵を決意しました。
元治元年1864年6月15日、来島又兵衛らは遊撃隊300を率いて出立。
久坂も長州藩兵3千を率いて山崎天王山や宝山、伏見町長州屋敷などに着陣、挙兵の準備を整えます。
久坂は長州藩の罪を回復させるための嘆願書を朝廷に奉ずるのですが、薩摩藩士・吉井幸輔や土佐藩士・乾正厚、久留米藩士・大塚敬介らによる長州藩兵入京阻止の意見書が建白されました。
朝廷内部でも長州藩の処遇をめぐり、強硬派と宥和派が対立していました。
宥和派の有栖川宮幟仁・熾仁両親王、中山忠能らは長州の入京と松平容保の追放を訴えましたが、禁裏御守衛総督となっていた一橋慶喜は長州勢に退去を呼びかけ、会津藩擁護の姿勢を取る孝明天皇も長州掃討を命じ、やむなく久坂は挙兵を決意しました。
禁門の変
元治元年7月19日(1864年8月20日)、変が起こりました。
福原元僴が指揮する一隊が伏見街道で大垣藩兵と交戦しました。
国司親相が指揮する一隊は京都蛤御門付近で長州藩と会津・桑名藩兵が衝突しました。
益田親施が指揮する一隊は山崎方面に出撃、越前藩兵とぶつかりました。
長州兵は、一時は筑前藩が守る中立売門を突破し、京都御所内に侵入しますが、乾門を守る薩摩藩兵が援軍に駆けつけ、長州軍は敗退しました。
真木・久坂隊は遅れて到着し、その時点で多くの者が戦死したことを知りました。
この戦闘において、来島又兵衛が戦死、寺島忠三郎、久坂玄瑞が鷹司邸で自刃、入江九一は鷹司邸脱出後に越前藩士に発見され戦死。
桂小五郎は田島方面に脱出後、潜伏しています。
大敗を喫した長州勢は長州藩邸を焼き逃走。
会津藩も長州藩士が隠れているとされた中立売御門付近の家屋を攻撃し、火の手が上がりました。
この2箇所からの火の手が京都の町を焼き「どんどん焼け」と呼ばれる大火となりました。
北の一条通りから南の七条・東本願寺に至る広範囲に延焼は広がり、多くの家屋・社寺が焼失しました。
生き残った長州藩兵は、大阪や播磨方面に脱出を図り撤退しました。
敗残兵をまとめた真木和泉は兵を逃がしつつ天王山に立てこもり、会津藩や新選組に囲まれると小屋の火薬に火を点け自爆して果てました。
禁門の変の影響
御所に向けての発砲や藩主からの軍令書が発見されたことにより、長州藩は朝敵となりました。
さらに、この変による大火により、長州藩は京の民衆から恨まれることとなります。
これにより幕府は長州に追討軍を送ることになります。
それが第一次長州征伐です。
最後に
尊皇攘夷を掲げ、過激な活動を行っていた長州藩は京を追放されましたが、政局復帰を狙い、さらなる謀略を企てます。
それが露呈し、会津藩などにより防がれたことにより、長州藩内部では会津、薩摩憎しの風潮が高まりました。
そして起こった池田屋事件、禁門の変。
とうとう朝敵となった長州藩は、幕府から征長軍を向けられてしまいます。
このまま、長州は潰されそうになるのですが、薩摩藩の西郷隆盛は長州を討つのではなく、戦わずして収める方法を目指し動き始めるのです。
次回は第一次長州征伐を考えたいと思います。